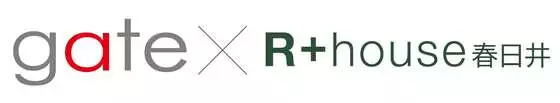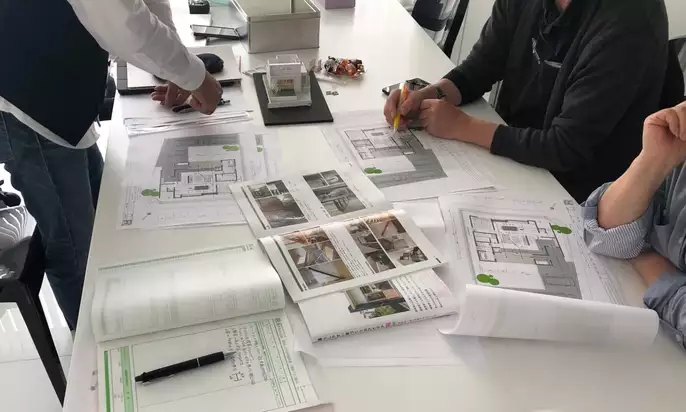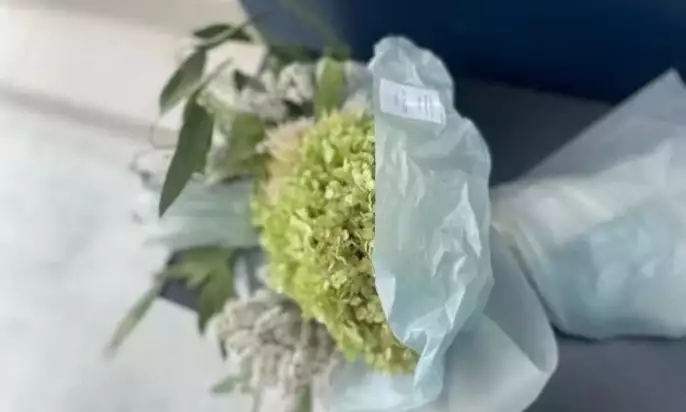今回は最後の⑩防音です!
そもそも音ってなんでしょうか?
もちろん聞こえるのが音なんですが、音は空気の振動で伝わってくると言われています。壁を隔てていても音が伝わるのは、音を受け取った壁(物体)が振動して反対側に伝わるとされています。
住宅においては、音を広げて伝えたい方は滅多に聞きませんが、音を抑えたいと思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
そこを今回はクローズアップしていきます。


防音の方法とは?
音が空気の振動によって伝わる事は、先にも少し触れていますが、そうなんです、振動させる空気がないと音が伝わらないんです。
え?宇宙はどうなんですかって?
もちろん音が伝わらないです。
「それなら真空で覆われた住宅なら音がしないの?」そういう事になりますね。
だだ、真空で覆うことは物理的に難しい事と、無音は外で何が起きているのかが全くわからないのも不安なので、あまり好まれる空間ではない気がします。
では、
音を伝えにくくする方法はなんでしょうか。
3つあります。
①吸音
②遮音
③ノイズキャンセリング
③のノイズキャンセリングはデジタル技術で、騒音を拾って逆位相の音で打ち消す技術です。あまり住宅に向いた話ではないので、今回は割愛します。
吸音と遮音の違い
①吸音と②遮音ですが、言い換えてみると①は吸収②は跳ね返すといったイメージです。
①は多くの凹凸を付けた壁、あるいは多孔材の凹凸に入り込んで、音がぶつかり合ってやがて小さくなり、壁の裏側には伝わらない音量になって聞こえなくなります。
②は音が振動となって伝わるのを防ぎます。
壁が重ければ重いほど、厚ければ厚いほど、密度が高ければ高いほど、振動は壁を通過する迄に音量が小さくなり伝わりにくくなります。
壁は比較的、①②どちらでも音を抑える効果は発揮しやすいのですが、音がいちばん漏れやすいのは、扉と窓なんです。
実は、壁より扉と窓に防音性能を先に施す方が、結果が得られやすいと思います。
とは言え、音量に個人差はありませんが、許される音量には個人差がありますので、どのくらいの施工をすべきかは、難しい部分があります。

住宅における防音について
吸音と遮音の違いが分かったところで、住宅における防音について考えてみます。
音楽における楽器や歌の音は、建物の外に漏れにくくする効果を期待しますが、日常的に家族の声や振動などは「小音」とするのが妥当かと思います。
音楽における楽器や歌の音は、建物の外に漏れにくくする効果を期待しますが、日常的に家族の声や振動などは「小音」とするのが妥当かと思います。
なぜなら、外の音があまり聞こえないのもリスクがあると考えているからです。
雨が降ったり、雷が鳴ったりが聞こえないと、お洗濯物を取込み遅れてしまうことになりかねません。また、サイレンや警報といった緊急のお知らせなど、多少外の音が入ってくる方が、不安がないと考えます。
先にも触れたように、住宅での音漏れの多くは、窓、もしくは扉にあります。音の振動を抑えられなかったり、どうしても隙間があって音漏れになります。と言う事は、防音は音を閉じ込めるために、防音ドアを採用したり、二重サッシにしたりする必要があります。それには、それなりの費用も掛けなければなりません。
と言う事で、住宅における防音とは、余程な必要性がない限り、扉や窓から音が漏れても良い、位な感覚で良いと思います。その上で壁には小音に置き換えられる施工を行うと良いでしょう。
では、小音に置き換えるには何が適しているのでしょう?
もちろん間取りや配置、音との位置関係がありますが、単に音を小音にするには、吸収するか跳ね返すかです。

小音にするには
A.跳ね返す
<プラスターボード>
石膏ボードは密度が比較的高く、比重は重め。枚数を重ねると効果は伸びていきます。一般的に使う材料なので、割と施工手間なく、予算も抑えられます。しかし、重ねる為、重ねる枚数によって、部屋は少しづつ小さくなります。
壁の中へ枚数を重ねてもよいですが、躯体部分のプラスターボードは薄いままになるので、少しの効果しか見込めません。
ただ、それなりに伝わる音量は少なくなりますので、家庭内や、外の雑踏など日常的な音が対象で、防音ドア性能までを必要としないレベルの方に有効です。
<コンクリート>
直にコンクリートを壁の厚さに打設します。厚さは10センチ〜13センチ程でしょうか。コンクリートは、プラスターボードよりも密度と重量を稼ぎやすいので、それなりの小音を叶えられやすいです。
ただし、費用もそれなりに掛かります。そして、この施工を望む方は、音楽家など、それなりの音の大きさを漏らしたくない方が選びますので、ドアも防音性能のある物に変えて、換気設備も必要になります。
この場合の換気設備ももちろん音を漏らさない小音施行が必要です。

B.吸収する
<各種断熱材>
吸音には、板状、繊維、発泡(フォーム材)、スポンジ、など様々な形がありますが、どれも役割は同じです。
発生した音が空気を振動させて壁にぶつかります。この壁にぶつかった音が跳ね返りまたぶつかって跳ね返り… これを繰り返して、やがて弱くなっていき、音は消えます。
発生した音が空気を振動させて壁にぶつかります。この壁にぶつかった音が跳ね返りまたぶつかって跳ね返り… これを繰り返して、やがて弱くなっていき、音は消えます。
壁に囲まれた箱の中のピンポン玉をイメージして下さい。箱の中でピンポン玉を内壁に強く当てると、箱の中をぶつかり続けます。しかし、やがてその力は衰えて跳ね返る力はなくなり止まります。音もそんなイメージです。
では、この壁の内側を穴や凸凹を付けてピンポン玉をぶつけてみたらどうなるでしょうか?
では、この壁の内側を穴や凸凹を付けてピンポン玉をぶつけてみたらどうなるでしょうか?
ぶつけられたピンポン玉は衝突エネルギーを分散させてしまい、跳ね返る回数は急激に減ってしまいます。このエネルギーを分散する状態が吸音です。
住宅建築の外周に使う断熱材が、この吸音の役割をしています。しかし、正確な断熱材施工と気密工事ができていなければ音は伝わってきます。言い換えると、正確な断熱材施工と気密工事ができていれば、外からの音を抑えることができるわけです。
こうなれば、室内の音を抑える事に集中できます。
こうなれば、室内の音を抑える事に集中できます。
音が伝わりやすい扉
室内の音は、キッチンの音、テレビ、お風呂、ドライヤーと様々ありますが、室内で音が1番伝わりやすい場所は、扉です。また、扉の形状によっても伝わりやすさが違います。
「開き戸」
開き戸は、閉じてしまえば音が侵入しやすい隙間が扉の上下だけ。
「引き戸」
引き戸は構造上、横にスライドさせる為、擦れないようにどこからも隙間が生じてしまいます。つまり、音が伝わりやすくなっています。
結論、音を気にされる場合は、壁の小音性能より扉の選択を「開き戸」に変えて「引き戸」は選択肢から外すように心掛けて下さい。更に、この状態ならば屋内の壁である間仕切り壁に小音性能を設ける事が効果的になります。
結論、音を気にされる場合は、壁の小音性能より扉の選択を「開き戸」に変えて「引き戸」は選択肢から外すように心掛けて下さい。更に、この状態ならば屋内の壁である間仕切り壁に小音性能を設ける事が効果的になります。
気になる程度なら壁材であるプラスターボードを2枚貼りするだけでも効果はありますが、できるだけ小音にしたいのであれば、間仕切り壁の壁体内にグラスウールを充填する事をお勧めします。できるだけ、厚めで重いグラスウールが望ましいです。それでも物足りないなら防音性能扉に換える事をお勧めします。

まとめ
音の不快感は個人差があり、音質、音域、音量が様々で、本人にとって、どの位の静けさが落ちつくのかは感覚であるため、一定の数値(〇〇dB)で基準を定めるのは難しいです。また、外の音が聞こえない程静かになると、今度は中の音が反響してしまい、居心地はあまり良いとは言えません。しかも反響を取り払う為に吸音工事を追加するなどとなれば更に音から孤立してしまいます。
高気密高断熱住宅では、前述した内容を照らし合わせますと、必然的に外の音が聞こえづらくなりますので、事前にモデルハウス見学やオーナーズハウス見学などを活用して、音の感覚を確かめられる事をお勧めします。
高気密高断熱住宅では、前述した内容を照らし合わせますと、必然的に外の音が聞こえづらくなりますので、事前にモデルハウス見学やオーナーズハウス見学などを活用して、音の感覚を確かめられる事をお勧めします。
最後に
それでは、皆様が後悔しない夢の家づくりを叶えられますように。